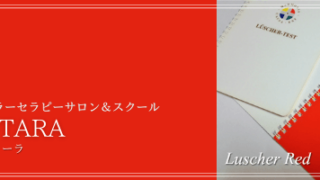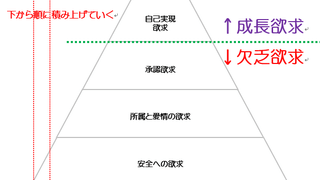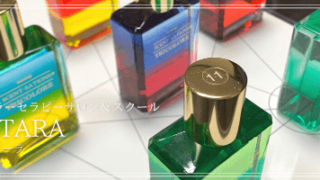前期石器時代(35万年前)わたしたちの遠い祖先は赤土で刺青をし、赤土で遺骨を彩色しました。
旧石器時代にはラスコー(2万年前)やアルタミラで赤・黒・黄・茶の顔料で彩色された洞窟壁画が描かれています。わたしたちははるか昔から「この地上の色とともに生きていた」のです。
クロマニョン人の彩色
色彩史で1番最初に登場するラスコーやアルタミラの彩色壁画は、人類が色彩を意図的に用いた証(壁画)が残存する最古の遺跡です。
狩猟採集時代~狩りをし木の実を採取し食べるものを得る~に自分たちが生き延びるため、または人類の種の保存・進化のためには「農耕・酪農の知識や技術」を得る方が重要です。
しかしクロマニョン人は「生存が関わる」農耕技術より遥か昔に、顔料を発見し彩色技術を身に着けていました。

17年開催のラスコー展で再現された彩色壁画
人類が農耕や牧畜の知識や技術を手に入れ新石器時代に突入するのが8500年前。文明誕生が約5000年前。ラスコー壁画は2万年前。フェイバー・ビレンは、
との言葉を残してます。「人類が意図的に色を使いはじめた」のは文明興隆から遥か遡る後期石器時代なのです。
なぜ人類の祖先は、色を使おうと思った(彩色壁画を描いた)のか?
このロマンチックな謎は多くの研究者を魅了してきました。
彼らが居住していた洞窟の入り口付近ではなく洞窟の奥深くに壁画が描かれていること、すでにシャーマン的存在がいたことから、
自然物の色と形を自分たちの手で再現することで、呪術・儀式として用いられていた。
と考えられてきました。
が、動植物を祖先とする祖霊崇拝なのか、食の対象である禽獣を描くことで豊猟を祈願したのか、それとも狩の余暇の娯楽…芸術なのか?
文字を持たない彼らが「絵を描き、色を塗った意図」は謎のままです。

シャーマンを描いたとされるトリ人間。「鳥の被り物をした人間」であろうと言われています。
不可思議な紫色
ラスコー壁画は様々なトーンの茶~黒で彩色されています。
元来「自分たちの生活環境に多くある自然の色」は「手に入りやすい天然素材」とイコールで結ばれます。ラスコー(フランス)では有色土(オーカー)が多く採掘されます。赤や黒の顔料は入手しやすかったでしょう。
黄色の顔料になる黄土もまた世界各地でよくある顔料です。黄色~赤、茶、黒といった色は、彼らが生きる糧として狩る禽獣たちを写実的に描くのにも適しています。身近にある顔料で身近にある・自分たちの生命に関わるものを描いたとすれば理にかなっています。
不思議なことに、緑の顔料は豊富にあるのに使用された形跡がないようです。
青は彼らが色付けしたいと思うほど身近な色ではなかったのか、青色鉱物がこの周辺にないから描かなかったのか。なのに、さらに不思議なことに、パイソンの足元、後ろ足の下には9マスのスクエアが描かれマスが赤・黒・茶…と塗り分けられています。

岩絵の具の再現
前述したように、赤・黒・茶は顔料も入手しやすく彼らにとっては「身近な自然・禽獣の色として馴染みある色」。
青は使用されていない。しかしなぜかスクエアにはだけ「紫色」が塗られています。
当時のラスコー地域に紫の顔料になる天然物があったのか?しかしラスコー壁画で紫色で彩色されているのはこのスクエアだけです。
また、他の壁画…写実的な禽獣たちの描画に比べて異色を放つスクエア&紫色は「何を描いたのかわからない」ままです。
- 特別な形(しかも集合体ということは、画を描いた集団のサイン?)
- 特別な色(紫色)
おそらく紫色を含むスクエアは特別な願いか・祈願か・呪か…「特別な何か」の隠喩で描かれた特別なシンボルなのでしょうね。
石器時代から現代まで受け継がれる”神秘と謎の紫色”、おもしろいです。
石器時代の形のシンボル
前述したスクエアのように、壁画は色だけではなく多様な「形」も描かれています。

彩色壁画には「形」のシンボルも多用されています
集合的無意識に刻まれた基本図形は「線と点」から始まり、「四角」「三角」「丸」。
個人的に、最も根源的図形はエジプト文明で考えると「三角」かな?世界各地に普遍的に蔓延する円形(曼荼羅)を考えると「円」の方が根源的?と考えてましたが、
石器時代まで遡ると「四角」なんだ!
と思いました(笑)
彼らが何を「意図して」四角のマス目を描いていたのかは、やはり謎なまま。なんですけどね。
顔料と色の意味
この記事は、2017年ラスコー展に行った時のものをピッキングしてます。
フランスのラスコー現地に行っても保全のために現物は見れず、世界各地で開催されてるラスコー展の壁画(この記事の写真も)はすべて復元・再現です。
現代の天然画材はとてもお高いですが、原始~中世までの長い間は人工顔料自体が存在せず、自然物を原料にして彩色出来るようにしなければなりません。
研究者たちは洞窟の壁や出土された石更に残った石片を採取、材料を特定し(それが洞窟内もしくは周辺で採取できるのか)、添加物の有無を調べ…顔料を再現し、壁画を復元しています。
(復元は仏教壁画や宗教画でもよく行いますが、石器時代からの復元は自然環境の変化も大きいでしょうし大変な作業だと思います)
クロマニョン人は自分達の周囲にある自然物を「生きるための採取」をするのみならず、彩色可能な技法にまで発展させてたのですね。色や彩色に向かう、どんな情動や情熱がそれをさせたのか。ロマンですよね~。

カラーセラピストのための色と自然のあれこれ
わたし自身も岩絵の具や水干絵具で仏画を描きます。
日本画材は「粒子を量り売り」します。
当初、サラサラした「粒子(砕いた貴石や土など)」をどうやって画布に定着させるのか不思議で仕方ありませんでした。後に「膠(動物のゼラチン質。加熱すると粘度が出る)」を混ぜて絵の具にすると知った時、
と感心してました;
最初に混ぜたのはクロマニョン人で、ラスコー壁画も膠を混ぜて彩色されています。まさか石器時代からの伝統とは。。。文明興隆後は、
「美しい天然の色(もしくは加熱や紫外線で美しい色に変化する)を持つ自然物」に
「膠」を混ぜて彩色する
この方式が確立されると、希少性が高く高価な自然物~貴石は顔料・染料としての価値も高くなります。
2015年のカラーセラピスト勉強会は「自然の色」
基本に立ち返る…ということで2015年の勉強会は「自然からの色のイメージ」を1年間お伝えしました。
毎回「クロマニョン人になった気分で●色を見ると~」という風にスタートしてシェアしていただいてましたので、この記事が参考になると嬉しいです☆